マーケティングコンサルタント GAEA<ガイア>松野恵介




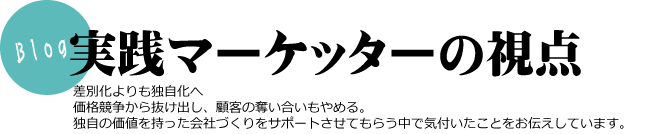
僕自身の経験で、ものすごく勉強になったことのひとつに
「書籍出版」があります。
これって、本当に勉強になることが多いのです。
少なからずコンサルタントという職業を続けていると、
何度も講演を聞いてもらう人や、仕事を頂ける人が出てくる。
「あぁ、伝わっているんだ」という実感もわいてくるわけです。
聞いてくれる人に伝える。
コトバを変えると、好きと言ってくれる人にシッカリと伝える。
これは、スゴク大切なことなんですが、
時として、それはキケンな要素も秘めている。
以前に、こんな話を聞いたことがあります。
+++++++++++++++++++
漫才を何年もやっていて舞台にも立っていると、
少なからずファンという人が付いてくる。
目の前のファンに思いっきり笑ってもらうのは大切だけど、
それだけだと見誤ってしまうことがある。
ファンというのは何を言っても反応してくれるし笑ってくれるから。
ファンを笑わせるのは簡単
一番簡単に笑わせられる人を、必死に笑わせにいったときに
それを見て「なんだ、あいつ?」と引いている人の存在を意識できるかどうか。
ファンが騒ぐその奥で、テレビに座ってみている人を笑わせられるかどうか。
本当に笑わせないといけない人は誰なのか?
そうやって考えていかないと、その笑いはすぐに時代遅れになる。
+++++++++++++++++++
というようなことを、島田紳助さんが言ってたのを覚えています。
これを知ったときに、僕自身に置き換えてみてゾッとしました。
「安易に笑いを取りにいってるんじゃないか」と。
僕自身、メルマガに始まり、ブログ、SNSなど、
書いて発信するということを続けてきています。
その中で、「読んでもらっている人だけ」「好きな人だけ」ではなく、もっと多くの人に伝えていくためには客観的な指標が必要。
それが「書籍出版」だったのです。
もう少し詳しくいうと、書籍出版をしていく中で、気付かせてくれるのは編集者の方です。
編集者の目や声が、ひとつの物差しとなり、僕の書くことを見なおしていくきっかけになっていることは間違いありません。
書籍出版というと、
「俺には関係ないよ!」
という方も多いかもしれませんが、
「書くこと」「書いて発信すること」を考えてみてください。
これからどんどん「書くこと」で発信する時代が進む中で、
編集者が何を見て、何を考え、どう消費者に届くコンテンツに仕上げていくのか?
・売れる本とは?
・読者の知りたいこととは?
・構成の仕方、見出しの考え方は?
・タイトルの付け方、前書きの要素、メッセージは?
これを、一度は押さえておくのと、おかないのとでは大きな違いが出る。
そう実感します。
ただ実際には、なかなか編集者に触れる機会がないのも事実なんですが、実はそれらが全てこの本の中に書かれているんです!
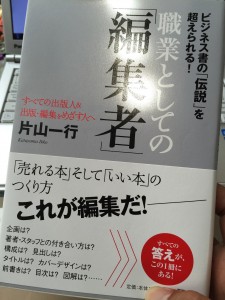
著者の片山さんは、40年以上ビジネス書を作り続け、たくさんの著者と触れる中で、書くことについて語っておられることは役立たないわけがない。
書くことを続けている人に、おススメします!
←NEXT 教授になるための論文
「バランスのとり方」が大切 PREV→